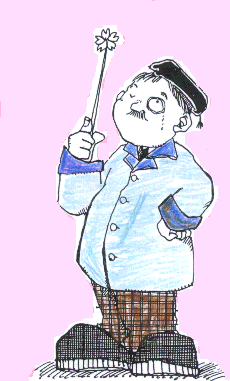
八重 7〜30枚
菊咲 300〜350枚(兼六園菊桜)
○ カンヒザクラ 1〜2月
○ カンザクラ 2〜3月
○ ソメイヨシノ 4月
○ ミネザクラ 5〜6月
○ フユザクラ 11〜12月
病害虫に弱い(テングス病やコスカシバという害虫)
根元を踏み固められると呼吸困難になる
太い枝を切られると枯れてしまうこともある。ゴツゴツとした幹を見て「頑丈な奴」だと思われているかも知れませんが、本当はとてもデリケ−トなのです、花の咲く頃だけでなく、新緑の頃、紅葉の頃、そして寒い冬の頃にもあたたかく見守り声をかけてあげてください。
の由来は
日本最古の文献「古事記」の中に「木花之佐久夜毘売」(このはなのさくやひめ)という美しい女の神様が出てきます。
桜の古名は「木の花(このはな)」といい、「佐久夜」が転じて「佐久良(さくら)」になったという説、他には、花が麗らか
に咲く「咲きうらら」が”さくら”になったという説、はたまた樹皮が裂けるから”さくら(裂)”から転じたという説などいろいろあります。
これらのほか、日本では古来観賞用に栽培されていただけに固芸品種が多数あり、これらはその細かい系統いかんにかかわらず、サトザクラ(里桜)としてまとめられる。そのうち大多数は広い意味のヤマザクラ系のサクラて,特にオオシマザクラ系統の品穫が多い。またヤマザクラ系以外のサクラとの間種と推定される品種も多い。花には、一重咲〈ソメィヨシノ,寒接(かんぎくら)),ハ重咲,菊咲、二段咲かあリ、また種子から数年で開花する幼型〈ワカキノサクラ〉も知られている。花色も白色から、やや濃い桃色までが多いが,緑化して黄緑色となったもの(鬱金〔うこん)、御衣黄(ぎょいこう))も知られている。子房は1個が多いが、まれに2個のものや、また葉化した品種(昔賢象(ふけんぞう)、一葉(いちよう)、関山(かんぎん)〉もある。
サクラは古来万葉集など詩歌にうたわれ、愛されてきた。ウメに代わって左近の桜が植えられたのは桓武天皇の時代といわれる。
八重咲のサクラは平安時代にすでに知られていたが、特に江戸時代に入ってからは多数の品種が育成され、今日に残っているものが多い。用途としては、材は版木として重要で、細工物にもよく.樹皮はタバコ入れなどの細工物となるほか、これから咳(セき〕止薬が作られる。八重咲の品種の花を塩漬にしたものは熱湯に入れて祝事に飲用、オオシマザクラの葉は桜餅(もち)を包むのに使う。繁殖は実生〔みしょう)、接木、挿木などによる、大気汚染には弱い。なおサクランボは同じサクラ属の果樹オウトウ(セイヨウミザクラ〉の果実をさす。